ブックレビュー 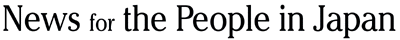 |

|
『裁判の中の在日コリアン』
在日コリアン弁護士協会 著
現代人文社 刊
|
「日本を照らす鏡――在日コリアン」
著者である協会は北でも南でもない在日コリアンである弁護士50名が集う団体である。本書はまず在日コリアン形成の歴史と法的地位の変遷を概観する。
その上で裁判に登場した在日コリアンの人生をメンバーの弁護士たちがたどり、人間的共感をもって主人公たちの苦闘を記した。
「中高生の戦後史理解のために」 というサブタイトルにふさわしい平易さと、包容力に満ちた文体がそろう。
評者は、やさしさとはレベルを下げることではなく、書き手が問題の理解を一層進め、もう一段抽象と飛躍を高めることだという考えをもっているが、
いくつかの文章はそのことに成功している。
たとえば、金嬉老 (キムヒロ)──寸又峡事件である。
金嬉老は在日二世だった。幼くして父を失い、母とともに学校裏の庭にある掘立て小屋に住み、投石のいじめや侮辱に会いながら成長した。
その日の米にも困る生活だった。飛び抜けて感受性の強い彼にとって、思春期は、打ちのめされては立ち上がる日々の連続だったに違いない。
そのような人生の到達の末にできあがった反逆の精神と肉体の統合、それが37歳の金嬉老であった。
ヤクザ者と警察が投げつけた言葉は彼の心深くにマグマのように蓄積された悲しみと憤り、それは限りなく公の憤りに近いものであったのだが、
その爆薬に信管を与えるようなものであった。
やくざ者へのライフル銃による殺伐とした暴力、警察への爆弾をもった突入の失敗のあと、
人質をとって旅館にたてこもって彼の人生の鏡に照らし出された日本社会の暗部を金嬉老はインタビュー画像で訴えた。
そこには現場にとびこんで言い分を聞いたジャーナリストの決死の行動があったことも記憶されてよい。
彼のうったえは心ある人々に届いた。その力――知力は金嬉老の被差別の人生の中で鍛えられたのだろうという叙述に余人には記せない筆者の共感がこもる。
それは事件の単純な説明の域を超えた響きをもつ詩(うた)といってもよいものだと思う。
この団体の代表李宇海 (イウヘ) 弁護士が書いた。
東京都の管理職を希望して拒否され、一審敗訴、高裁で劇的な逆転をとげたが、上告審で逆転敗訴した鄭香均 (チョンヒャンギュン) さんの物語も目を引く。
上司に薦められたこともあって応募した管理職試験だったが、人事課から電話があった。
「あなたは試験を受けられない。在日は (公務就任権がないという) 「当然の法理」 があるのを知らないのか」。
普通に人生を歩もうとするのに、こんなに厚い壁があることがどれだけの人に知られているだろうか。
東京都は高裁で完敗した。すぐに解決するはずの事件で主人公は7年も待たされた上弁論の通知が届いた。それは、逆転敗訴を示唆する出来事である。
在日のまま初めて弁護士になる前人未踏の道を開いた金敬得 (キムキョンドク) 弁護士 (故人) の弁論は、人生をかけた壮絶なものだったという。
ひょういつな表情に、いつも微笑みをたたえていた彼の弁論とはどんなものだったか。
暗く、圧迫感に満ちた石造りの大法廷にしみ入っていく在日第一号の法律家の声と、原告本人の胸中を察しながら読む。
掲載された文章の一つひとつは、ある種の包容力をもち、浸透力をもっているように思われた。
在日コリアン弁護士が在日コリアンの人生の苦難と苦闘に言及するのだから、そこに響きあう 「うた」 があるのは当然なのだが、本書の説得力は何故生まれたのか。
生活の実際の大変さといい、社会的なステータスといい、主人公と筆者たちには筆舌につくしがたい闘争の歴史があった。
この本に登場する主人公たちの人生の一つひとつは、自由と平等という近代の理念と矛盾する日本の社会の闇を照らし出し、
わずかだが、これこそ光だといえる根拠を示しているのではないか。
本書は在日コリアンの、ではなく、日本列島という場に住む私たちのかすかな希望をうたっているのである。
リベラル派を含めて、日本の知識人エリートの認識する宇宙には在日コリアンのことはすっぽり抜け落ちている。
本書でも正当に取り上げられているが、帝国日本が朝鮮半島住民に強制的に焼き鏝 (こて) のように記した日本国籍を、
サンフランシスコ条約締結で朝鮮半島への領有権を喪失したことを奇貨として、今度は日本に残留した朝鮮半島出身者から、
法律でもないいっぺんの法務省民事局長通達で剥奪した。そして国籍がないという理由で生きる権利さえ無慈悲に蹂躙した。
最高裁判所判例もこの措置を追認してきた。(塩見訴訟など) 残存する差別意識は、
こうした公権力の措置と世間の風潮によりかかってきた庶民の無意識の底に蓄積されてきた汚泥である。
歴史のこの経緯に言及するのは代表的な憲法基本書ではたった一冊しかない。旧 「帝国」 大学の教授たちの教科書にはただの一行も言及がない。
この歴史認識は歴史の中での自己像を確立できていないこと、すなわち自分を知らないことになるのだと思う。
市民社会――人間に内在する自由と平等という近代の希望 (あるいは夢) をこの日本で実現しようとすれば、帝国の作り出した歴史と恥部に苦しくとも光をあて、
それを制度上も精神の上でも乗り越えなければならない。
本書は苦難の人生を歩んだ人々による日本の闇を照らしだす鏡かもしれない。
評 梓澤和幸 (弁護士)
|