ブックレビュー 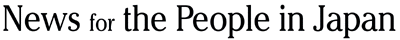 |

アーロン・グランツ(著)/反戦イラク帰還兵の会(著) TUP (翻訳)
『冬の兵士――イラク・アフガン帰還米兵が語る戦場の真実』
岩波書店 2009/8
木村 朗 (鹿児島大学教員、平和学専攻)
2008年3月の4日間、メリーランド州シルバースプリング市の全米労働大学でイラクとアフガニスタンからの帰還兵による 「冬の兵士」 公聴会が開催された。
その証言集会には200人以上が参加し、数十人の帰還兵がイラク・アフガニスタン戦争の実態を告白するとともに、
嘘で塗り固められた口実で戦争を開始したブッシュ政権とその嘘を隠す情報操作に加担したマスコミを告発する、勇気ある証言を行った。
主催者は 「反戦イラク帰還兵の会」 (IVAW、9・11以降に兵役についた米帰還兵の権利擁護団体で全米各地に組織をもち会員は約1500人)で、
イラクからの全占領軍の即時かつ無条件の撤退、すべての退役軍人および帰還兵の医療保障その他の給付、イラク国民への賠償支払、
の三つの目標を掲げている。また、「冬の兵士」 とは、ベトナム戦争帰還兵が1971年に開いた反戦集会の名前に起源をもつ。
本書は、この全米労働大学の 「冬の兵士」 公聴会とその2ヶ月後に連邦議会で革新系議員団が主催した 「冬の兵士」
フォーラムでのイラク・アフガニスタンという2つの戦場からの帰還兵たちの貴重な証言を中心に、
IVAWとの協同で独立系映画制作者チームが集めたイラク国内の民間人とヨルダン・シリアに脱出したイラク難民の証言も加えてTUPの翻訳で収録したものである
(その成果の一部は、「デモクラシー・ナウ」 で放送され、『冬の兵士―良心の告発』 (田保寿一監督)というドキュメンタリー映画にもなっている)。
本書に収められた帰還兵士たちの証言は、人を戦争向きに作りあげていく訓練・戦闘と様々なシステムがいかに残虐かを語ったもので、どれも生々しく重い。
非戦闘員への攻撃などを禁じた交戦法規が実際の戦闘で有名無実化していくさまを、
イラクに従軍したアダム・コケッシュは 「ファッルージャ包囲のあいだ、私たちは下着を換えるよりも頻繁に交戦規定を変更しました。
最初は “交戦規則に従え。決まり通りにやれ” でした。その後、“様子をうかがう不審人物は誰であれ撃ってよし” となった時期がありました」 と証言している。
ジェイソン・ウオッシュバーンは 「うっかり市民を撃ち殺してしまったときのため武器かシャベルを持参するんです。
その武器を死体の上に放り投げておくだけで抵抗分子のように見せかけることができるから」 と民間人を誤射した場合に行う隠蔽工作を暴露している。
また、ロバート・ザバラは、「新兵は全員 “殺せ” と返答することを求められています」 「あまり頻繁に口にしていると、
ナイフで喉をかき切る殺人テクニックを練習しながら何度も繰り返す “殺せ” という言葉が何を意味し、
何をもたらすかをまったく考えなくなります」 と兵士を非人間化し思考停止状態にする軍事訓練の実態を告白する。
マイケル・プライズナーは、司令部に始まる制度化された人種差別、
悪意を含んだ差別用語を使い始めたのは過去の戦争と同じく上官たちであったことを語っている。
特に、「ハジ」 という言葉は、メッカに洗礼した人というイスラム教では最高の尊称であったものを、
逆にイラク人を敵視して非人間化する蔑称として用いていると米国の欺瞞性を糾弾している。
このように、本書にある一人ひとりの証言は、無限にある戦場の真実の氷山の一角かもしれないが、
戦争の本質とそれが人間性に与える影響について圧倒的な説得力を持って迫ってくる。
なぜ兵士たちは、戦場体験について沈黙を守って 「英雄視」 されることよりも、たとえ 「非国民」 と呼ばれることになっても責任と良心を持って真実を語る、
より苦しい選択をあえてしたのか。戦地で自分たちが犯した様々な罪(無差別射撃などの残虐行為)を赤裸々に語ることは、
戦場で失われた自らの人間性とモラルを回復するためにもどうしても必要であったからである。
仲間の相次ぐ自殺や PTSD・自殺未遂という絶望の底から這い上がってきた 「本物の愛国者」 たちの数々の証言は、
IVAW現事務局長のケリー・ドーアティーが言うように、「占領中に行われる虐待は “一握りの腐敗分子” による不正行為の結果などではなく、
合衆国権力の最高層部で巧妙に作られた、我が政府の中東政策の結果だということ」 を明らかにするとともに、
「死と破壊に加わり、心身に傷を負わせる行為に加担してきた同じ人々が、自らの経験を公正で平和な世界を築くために転換することは可能だ」
ということの証明ともなっている。
本書を一読すれば、「これほどまでに真実に迫り、胸を打つ言葉を、この国の他の誰からも聞いたことはなかった」
という著者であるアーロン・グランツの率直な感想に読者の多くが共感するであろう。
本書は、開戦理由と帰還後の約束での二重の嘘を身をもって体験した帰還兵士たちによる、米国政府への捨て身の抗議文であると同時に、
そうした嘘を続ける政府に加担して情報操作を行っているマスコミに対する激しい告発状でもある。
帰還兵士たちが求めているのは、「法の支配」 の回復による無法状態からの脱出、マスコミの権力監視機能と真の民主主義の実現、
貧困と戦争をビジネス化して結合する腐敗した戦争経済・軍産複合体の克服である。ある兵士の 「私たちはテロリストと戦っていると教えられました。
ところが、本物のテロリストは私たちだった。そして、本当のテロリズムはこの占領だ」 という言葉がすべてを物語っている。
ミリバンド英外相が 「『テロとの戦争』 は誤りだった」 と実に感慨深い発言をしたのは、今年の1月のことであった。
同じ1月に登場した米国のオバマ新政権は、「テロとの戦争」 の継続を宣言し、
主戦場をイラクから移されたアフガニスタンでは隣国パキスタンを巻き込んでさらに泥沼化する様相を呈している。
2001年の9・11事件以来ブッシュ米政権を全面的に支持してきた日本では、政権交代を実現した民主党を中心とした鳩山連立政権が、
「テロとの戦争」 への対応の全面的見直しを迫られている。
この 「テロとの戦争」 は、決して他人事ではない。私たちは、まさに「この人たちの物語から目をそむけてはならない。
それはあなたの物語でもあるのだから」 という本書の冒頭にあるアンソニー・スフォードの言葉と真正面から向き合わなければならない。
(『図書新聞』 2009年11月7日号に掲載)

 |