ブックレビュー 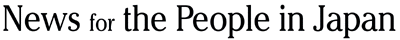 |

辺見 庸 著 『水の透視画法』
共同通信社 (2011/6/15)のお勧め
木村 朗 (鹿児島大学教員、平和学専攻)
本書は、作家の辺見庸が2008年3月から大震災直後の2011年3月まで、
共同通信を通じて全国加盟各新聞社に月2回配信した同名の連載企画 「水の透視画法」 (計74回)を中心に、
書き下ろしの 「予感と結末」 など3編を追加してまとめたものである。
本書を通読した読者は、ノンフィクションの世界に新境地を切り開いた初期の作品 『もの食う人びと』 以来の、
辺見庸の神髄が遺憾なく発揮された詩集 『生首』 (中原中也賞受賞作)と並ぶ伝説的作品の一つとなるであろうとの予感と、
ここに収められたエッセイ風の文章がまさにその本質において詩そのものであるという事実に気づかされよう。
また、その稀有な表現者の透徹した眼から見た社会と世界、
そして何よりも 「人間の底なしの内面」 の有り様を極限まで高められた感覚と、
辺見庸ならではの独特の言語(「ことば」)で表現された文章の一つ一つに思わず引き込まれる何かを感じるであろう。
辺見庸自身が、「茶子粒のようなものごとの細部と世界規模のマクロ、ないしは、ひとの内面と巨大な外的現象をあえて等量的に、
ていねいに表わすことばの画法」、「実験的といえなくもない新たな遠近法」 であると語る 「水の透視画法」 はもはや完成形の域に達し、
単なるエッセイを超えて、詩的な文体を通じた予言者的な警告を含む新しい文明批評となっている。
本書を辺見庸は、「予覚」、なにか予感のようなものに背中を強く押されて描き続けたという。
「戦争や大震災など絶対無比の災いのまえには、なにかしらかすかに兆すものがあるにちがいない」 との勘にもひとしい考えがあり、
作家のさだめは、そうした兆しを探し求めて表現することにあると語る。
辺見庸は、日常に兆すかすかな怪しげな気配を五感の全てを研ぎ澄まして感じながら、自己と他者に常に実時間で問いかける。
<ひょっとしたら世界は今静かに滅びつつあるのではないか。いや、自分がまっとうな見当識をうしないはじめているのか>、
<個のないところに愛はあるのか>、<この国にはいわゆる society という意味での社会はあるのだろうか>、
<プレカリアートは怒っていないのか、団結しないのか>、<民主主義とは “権力のレトリック” 以上のものではないのではないか>、
<どうやら資本が深くかかわるらしい “原発悪” が、ほうぼうに遠隔移転して、すべての人のこころにまんべんなくちりひろがってしまった状態が、
いまという時代の手におえない病状ではないのか>、
<見たこともないカオスのなかにいまとつぜんに放りだされた素裸の 「個」 が、愛や誠実ややさしさをほんとうに実践できるのか >、…と。
その辺見庸の視線は、安全地帯の高みから世界を睥睨する鳥の眼ではなく、あくまでも地べたを這いずり回る虫の眼である。
病魔と闘いながら人倫の根源的立場から資本、権力、メディア、人のあり方を問い続け、
社会(国家)と人間(個人)、自己と他者の関係性を省察してきた辺見庸の 「ことば」 は、
大震災で故郷の宮城県・石巻を失った痛みと悲しみのなかでいよいよ本質に迫る深みを増そうとしている。
辺見庸のことばは、まるで全身を締め付けてくる真綿のようで、静かではあるがずっしりと重い。
あまりにも理不尽な社会への怒りと不甲斐ない自己と他者に対する無力感をこころの底に秘めているからであろう。
善と悪の境界線を喪失して病の自覚もなくなった社会、個の表現を無意識に殺す悪意なき無言の諧調、死刑を黙認する心のありよう、
万人が被害者であり加害者でもある世界、悪の根源をとらえる視力をなくした世論の短絡ぶり、個をおしのけ例外をみとめない狭隘な団結、
非常事態下で正当化されるであろう怪しげなもの、あぶない集団的エモーションのもりあがり、たとえば全体主義、…等々。
「畏れよ」、「われわれはこれから、ひととして生きるための倫理の根源を問われるだろう。
逆にいえば、非倫理的な実相が意外にもむきだされるかもしれない。つまり、愛や誠実、やさしさ、勇気といった、
いまあるべき徳目の真価が問われている」 という辺見庸のメッセージに静かに耳を傾ければ、隠された社会の闇と人間の実相が浮かび上がってくる。
しかし、決して絶望しているわけではない。
むしろとことん絶望することで生み出されるであろう何か(ことばと人間性の回復)に一縷の希望を見いだそうとしているのだ。
最後に、この時代の闇と人間の内奥に真摯に向き合った類い希な作品と出会い、
非人間的なるものを根源的な人倫の立場から問う言葉の重さを噛みしめる機会を得たことの幸運を感じるのは評者だけではないと思う。
いずれにしても、詩人・辺見庸の存在と彼が説く 「未来への予感」 「忍びよる破局」 から私たちはますます目が離せなくなった。
この 「予覚」 を吉凶いずれに転じさせるかは、これからの私たち一人ひとりに委ねられている。
「新しい日常」 と 「新しい秩序」 もそこから生まれてくるに違いない。
(『図書新聞』 2011年8月号への寄稿)

 |