ブックレビュー 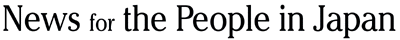 | 
書評 『検証 福島原発事故・記者会見』
日隅一雄 木野龍逸 著 岩波書店
梓澤和幸
政府、東電は福島第一原発事故について真実を語っていないのではないか。マスメディアは政府、東電の痛いところをついていないのではないか。
この疑問はさらに不安をもたらす。この国に生きて、私たちは自らを、妻、子、孫、そして友人たちを守って生きていけるのか。という思いである。
そういう問いに著者たちも駆られて行動した。その記録が本書である。
膨大な資料の読み込みも行われた。
著者の一人、日隅一雄は3月11日の震災の際、弁護士として東京で仕事をしていた。木野はジャーナリストとして。
やがて二人は2011年3月から2012年1月にかけて、110回をこえて東電の記者会見に通い続ける。
なぜこの現場に吸い寄せられたのか。その動機に迫る前に、隠蔽された事実について、本書の説くところをひいてみよう。
〈メルトダウンとレベル7〉
福島第一原発がメルトダウンしていることを東電が正式に認めたのは、2011年5月15日である。
この日は1号機についてだけで、2、3号機もメルトダウンの可能性を認めたのは5月24日である。政府・保安院は6月6日であった。
ここまで事実が隠されていたことは類書も説く。しかし、本書は現場にいる一人一人の生きた人間が伝える表情と言葉で、
犯罪的とも言うべき情報隠匿を明らかにしている。
原子力保安院を代表する記者会見で、中村幸一郎審議官、根井寿規審議官はメルトダウンを認めていたが、この二人は主役から退かされた。
代わりに登場したのは、メルトダウンを否定する西山英彦審議官であった。
このことで政府の避難対策は明らかに遅れた。情報を隠して嘘を言わせている誰かが、保安院の内部か、政府の中にいた!!
固有名詞もあがる役人たちの、自信がありそうな、逆におどおどしたような表情。その描写は臨場したものだけに許されるリアリティーで裏付けられる。
〈SPEEDI 〉
SPEEDI とは放射能物質拡散予測システムである。政府が開発し、文科省が運用している。
これによって避難の経路、範囲、ヨウ素剤の配布などの対策をうてる。
政府はSPEEDI の予測を公開しなかった。しかし、文科省の中ではこのシステムにより、高線量予測地域を認識し、
独自にモニタリングカーを使って計測していた。
浪江町の赤宇木地区ではひどい線量を政府は認識していたが避難指示を出さず、住民は知らずにいた。NHKの取材陣に聞かされ、3月末退避した。
国会での追求で、3月12日から24日までに乳児の甲状腺にかなりの影響を与えることも明らかになった。あまりに悲惨な被害である。
誰かがSPEEDI の情報を止めた。各メディアの記者や著者たちは食い下がったが、犯人は誰か、それはいまだに明らかになっていない。
〈汚染水、海洋投棄〉
福島第一原発では、通常の冷却システムが破壊された。外部からの水の注入によってようやく冷却を保っている。
大量の高濃度汚染水があふれ出てくる。この汚染水の処理は2011年3月の水素爆発以来、政府・東電にとって優先的な検討課題のはずであった。
テレビ、新聞では識者がメガフロート(海上に浮かべたタンク水船のようなもの)を曳航して来る案も提案されていた。
それらの検討の経過は明らかにされないまま、4月4日東電は保安院の許可を受けて汚染水の海洋投棄を始めた。
誰がこの決定に責任を持っているのか。具体的な個人がいかなる利益衡量の末に、いかなる価値判断をして環境を汚染する決断をしたのか。
この決断が発表された4月4日、著者らは会見の場にいた。東電の担当者は何回も問う著者たちに、誰が決めたか答えない。
少なくとも保安院に許可を求めた者はいるはずだ…。食い下がる著者たちに、ついに東電武藤栄副社長が保安院に許可を申請したことが明らかになった。
しかし、決断を下した責任者はついに明らかにされない。この間、午後4時以降の会見は、午後11時30分から午前1時45分までという深夜の時間に及んだ。
食い下がる日隅たち。
しかし、マスメディアの記者たちはパソコンを拡げ、カタカタ、カタカタという音をさせたまま誰一人声を上げない。
日隅たちは、追求をいったん止めざるを得なかった。
数十人の取材陣。10台は並んだテレビカメラ。3人でいっぱいになる答弁者席。
真実を追うものがあたかも冷笑されるが如き光景。もうこの頃、がんの病巣は日隅の体を襲っていた。
この記者会見記録は無味乾燥なジャーナルではない。日隅、木野という二人のジャーナリスト(ここでは、日隅は弁護士というより、
NPJという市民メディアの記者として振る舞っている)の壮絶な格闘記録である。
ある気負いをもってこの場に乗り込んだというより、何だ? 変だな、この場所は、という小さな疑問をもって取り組んで行くうち、
垂直の 「権力の壁」 にぶつかる。マスメディアの記者たちもときにともに追求にたつが、ときに沈黙、そしてときには日隅たちに厳しい声をあげたこともある。
(俺たちはなぁ、送んなきゃ向こうからどうしたって催促が入るんだ。その場の正義感だけでこの記者会見の場を使ってくれんな・・・)
とでも言いたげな雰囲気である。
でも、これを放っておいては福島の人たちの暮らしはどうなる?
子どもたちの命はどうなる?
8時間も10時間も立ったり(椅子がなく)座り続け、疲れ切った体を励ましながら、著者たちは通った。
注意深く読んでいくと、登場する人物は単純な悪役でも善人でもなく、一人の人間として描かれていることに気がつく。
家に帰れば家族もいて日々を生きている人間として。
東電の答弁者も、保安院の役人も、そして若い記者たちも。
ここで私はノーマフィールドが評伝 「小林多喜二」 (岩波新書)で多喜二を語っていることばを思い出した。
「ここ(多喜二の小説)では、階級の敵にさえも、役割が与えられている」
人を受け入れる著者本来の性格がそれを可能にする。
「それは作家としても、活動家としてもとても大切な資質なのだ…」
作者は時にブログで “マンションから飛び降りたいくらいだ” という程のガンの痛みを訴える。
他方、私(たち)の不勉強、不作為が原発被害者の苦しみをもたらしたのだ。
その苦しみに比べて私の病の痛みは小さいくらいだ、ともNPJインタビューで答えた。
この本に一本の太い線のように貫かれているのは、そうした一人の人間の悔恨と、「もう下がらないぞ」 という心の奥深くに生じた決心──。
それは良心という表現がもっとも当てはまるだろう。本書は良心の闘争の記録なのである。
運命の力が、痛みをほんの少しでも減ずるように祈りつつ、書評の筆を措く。

 |